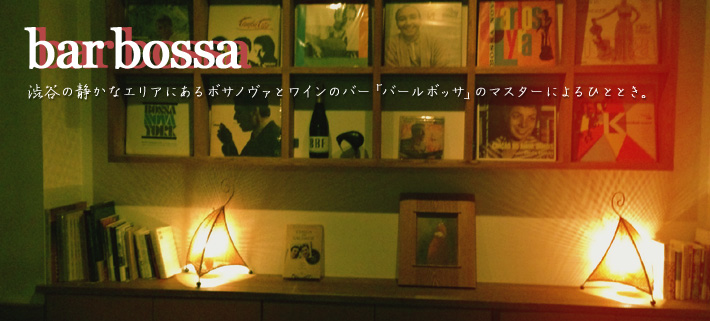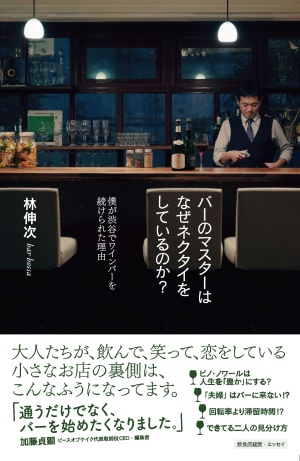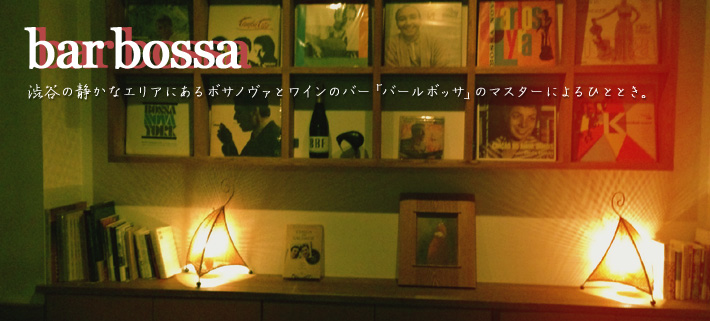
vol.39 - お客様:岩間洋介さん(フィンランド・カフェ moi)
「真ん中よりも、ちょっと外れたところにいたいひとのための10曲」
いらっしゃいませ。
bar bossaへようこそ。
今月は吉祥寺のフィンランド・カフェ、モイのマスター、岩間洋介さんをゲストに迎えました。
林(以下H)「こんばんは。」
岩間(以下I)「こんばんは。ラムトニックを、薄めでお願いします。」
H「懐かしい注文ですね。岩間さんがお店を始める前は、仕事帰りによくbar bossaに立ち寄ってくれて、この薄めのラムトニックを作ってました。さてさて、お生まれは東京ですよね。」
I「はい。1966年東京生まれ、魚座の一人っ子です。典型的な『昭和の団地っ子』として、会社員の父親と専業主婦の母親のもとで育ちました。両親ともに音楽を楽しむ趣味は持ち合わせていなかったので、おもにテレビやラジオを介して、ひとりで、音楽と出会い、自分なりの世界を広げていったという感じです。」
H「1966年、僕の兄と同い年ですね。音楽は自分なりの世界を広げたということですが」
I「まず最初に夢中になったのはクラシックでした。きっかけは、小学生のときテレビでやっていた『オーケストラがやって来た』という音楽番組。出演していた指揮者の小澤征爾が、とにかくカッコよかった。長髪を振り乱し、変なネックレスをじゃらじゃらぶら下げて、しかも奥さんはハーフのモデルで...... これはもう、指揮者になるしかない!! とすぐさま銀座の山野楽器まで指揮棒を買いに走りました(笑)。楽器はおろか、楽譜すらまともに読めなかったのですが(笑)。」
H「指揮棒、買っちゃいましたか...」
I「当然、初めて買ったレコードもクラシック。アバド指揮ロンドン交響楽団の『ロッシーニ序曲集』でした。団地内にあった『十字屋』というレコードショップで買ったのですが、ジャケットを見るといまでもそのときの光景がよみがえります。ダウンロードだとこうはいきません。でも、じつは当時いちばん好きだったのはオーケストラのチューニングの音でした。あの混沌とした響きを聴くと、なんだか気持ちがザワザワして鳥肌が立つんです(笑)。ずいぶん馴れましたけど、いまでもそれは変わらないですね。」
H「中学生以降はどうでしょうか?」
I「中学から高校の前半までは、とにかく『佐野元春』でした。ちょうどフォークからニューミュージックへ邦楽の主流が移り変わろうという時期で、YMOの登場もその頃です。そんなとき、自動車のCMに使われていた『Catch Your Way』という曲で杉真理(すぎまさみち)を知ります。聴いた瞬間『これだ!!』と思い、すぐ『十字屋』へと走ったのですが、ぜんぜん見つからなくて...... もしやと思い覗いてみたら、案の定『女性ポップスさ行』のコーナーに紛れていました(笑)。『ナイアガラトライアングルVOL.2』の2年くらい前のことです。そうして、杉真理の周辺をいろいろ聴いてゆくなかで『発見』したのが佐野元春でした。」
H「佐野元春!」
I「人工的な光とコンクリートの建物に囲まれて育った東京の団地っ子にとって、佐野元春の音楽、とりわけ詞の世界はリアルとはいわないまでも、じゅうぶん共感できるものでした。音楽を聴いてそんなふうに感じたのは初めてのことだったので、いっぺんで引き込まれてしまったんです。友人と、都内や横浜でのライブは片っ端から行きましたし、ビートニクに興味を抱いてアレン・ギンズバーグの詩集を買ったりとライフスタイル全般に影響を受けました。それほど強い影響を受けたにもかかわらず、1983年、NYに彼が旅立つ直前におこなわれた中野サンプラザでのライブを最後に、少しずつ聴かなくなっていきました。嫌いになったわけではまったくなくて、もう十分沢山の宝物を貰ったので『卒業』したという感じなんだと思います。当時『ロックステディ』という邦楽の専門誌があって、『徹底研究』という特集企画がウリだったのですが、そのおかげでシュガーベイブやはっぴいえんどのような過去のバンドまで聴いていましたね。」
H「え、僕もその辺りが大好きだったのですが、岩間さんとそんな話、全然しませんでしたね... 他の音楽は?」
I「併行して、少しずつ洋楽も聴き始めていました。とはいえ、時代は『ベストヒットUSA』や『ビルボードTOP40』の全盛期、同時代の音楽にはまったく興味が持てなくて、NHK-FMで平日の夕方にやっていたオールディーズの番組ばかり聴いていました。当時はまだ『ソフトロック』とか『ガレージロック』といった便利な用語はなく、50年代~60年代あたりの音楽はすべてひっくるめて『オールディーズ』と呼ばれていたんです。モータウン、フィル・スペクター、A&M、フォークロック、サイケ...... いまにして思えば『闇鍋』のような番組でしたが、体系的にではなく、直観でおいしそうなものをつまみ食いするような聴き方が性に合っていた気がします。」
H「岩間さん、聴き方が本当に曲がってなくて正しいですねえ。」
I「そんなある日、突然『黒の時代』がやってきます(笑)。高3のとき、ラジオから流れるザ・スミスの『Reel Around The Fountain』を聴いて衝撃を受けました。『公共の電波にこんな覇気のない歌声を流していいのか!!すばらしい!!何者だ!!』というワケです(笑)。日本のテレビやラジオが取り上げないだけで、どうやらイギリスにはもっとすごい音楽がたくさんあるらしい。こうして、雑誌『フールズメイト』(ときには『DOLL』)を熟読し、西新宿~渋谷界隈の輸入レコードショップに足しげく通う日々が始まりました。そして、身につける洋服もどんどん黒くなっていきます(笑)。」
H「え、岩間さんってフールズメイト体験してたんですか。今からは想像できないですね。こういうのって本当に本人から聞かないとわかんないです... そして高校を卒業するわけですが。」
I「浪人~大学の半ばまでは、NW(ニューウェイブ)、まあ、いまでいうところのインディーズですが、にどっぷりはまっていました。よく行ったレコードショップは、西新宿の『UK EDISON』、それに代々木のボロい木造アパートの一室にあった『イースタンワークス』。ここは『フールズメイト』の編集部の人たちがやっていた店で、後の『CSV渋谷』の前身です。ところで、ひとつはっきりさせておきたいのですが(笑)、80年代のNWとは音楽限定のムーブメントではありませんでした。映画や美術、文学、思想、ファッションを含め、商業ベースに(あえて)のらないもの、無視されているものに対する総称としてそう呼ばれていたに過ぎません。極端な話、初対面のひとでも、そのひとのファッションを見れば、どんな音楽を聴き、どんな本や映画を好むのか瞬時に理解できました。『スタイル』というか、あの時代、NWって『意思表明』だったんです。そんなぼくがNWを『卒業』することになったきっかけは、ひとつはシスターズ・オブ・マーシーという最愛のバンドが来日を目前にして解散してしまったこと、そしてもうひとつは、87年くらいからインディーレーベルがどんどん大資本に吸収されて生気を失っていってしまったことが挙げられます。『詰んだ』という感じ。反動で、その後数年はひたすらクラシックばかり聴いていました。」
H「商業ベースにあえてのらないもの、なんですよね。わかります。」
I「教員になるような器ではなかったので、大学院を出て2年弱フリーターのようなことをやりながらオーケストラの事務局や音楽事務所で仕事をするチャンスを窺っていました。世の中には、なにか熱中できる対象をみつけたとき、趣味として一生楽しくつきあう道を選択するひとと、仕事として深く関わらずにはいられないひととがいます。どちらがよいとかわるいといった話ではないのですが、僕は常に後者なんです。そうして、渋谷にある『Bunkamura』という複合文化施設に就職し、都合8年、企画運営部というところで仕事をしていました。劇場で働いて初めてわかったことなのですが、劇場って、舞台にも客席にも誰もいないと本当につまらない、ただの『箱』でしかないんですよ。そこが、以前コンサートや芝居で自分が感激したのと同じ空間だなんてちょっと信じられないくらいに。つまり自分がずっとやりたかったことは、規模の大小ではなく、そのつまらないただの『箱』を特別な何かで満たすことなんだ、と気づきます。ちょうどそんなとき、友人から頼まれて『アメリカンブックジャム』という雑誌のイベントを手伝うようになりました。最初はポエトリーリーディングがメインだったのですが、渋谷エフエムで『Everybody Knows?』という番組をやっていた田仲君、東君と知り合ったのを機に、ひとつのキーワードを音楽・言葉・映像によって融合させるような実験的なイベント『Travelin' Word』をスタートしました。『Bunakmura』ではやらせてもらえない鬱憤を、そこで晴らしていたようなところはありますね。『bar bossa』さんや『Cafe Vivement Dimanche』さんにお邪魔するようになったのもそのころです。どこにも似ていない、世界にひとつだけの空間をこんなふうに個人でつくってしまった人たちがいる。驚きました。いつか自分もこういう場所をつくってみたい、そんなことをぼんやり考えるようになりました。」
H「『箱』を特別な何かで満たすこと! 岩間さん、すごい言葉が出て来ました。」
I「同じころ、ぼくが渋谷の『Bunkamura』で働いていた頃は、まさに『渋谷系』の全盛期でした。当時、会社の目と鼻の先にHMVがあって、その1Fの一角に面白いCDやミックステープを扱っているコーナーをみつけました。『渋谷系』発祥の地(?)とされる伝説の(?)『太田コーナー』です。邦楽も洋楽も、時代も関係なく、ただ自分の感覚という「ものさし」だけを頼りに音楽を串刺ししてゆく『渋谷系』の流儀に、ずっと無意識のうちにやってきた自分の音楽との付き合い方と共通の匂いを感じ取りました。あと、『渋谷系』にはバカラックやロジャニコ、いわゆるソフトロックの再発見、再評価という側面があると思うのですが、これは『渋谷系』の中心人物たちがぼくとほぼ同世代、つまり幼い頃、テレビやラジオを通してそうした音楽をいわば『子守唄』のようにして育った世代ということが大きいと思います。その後しばらくどっぷり浸かることになるボサノヴァをはじめとしたブラジル音楽を聴くようになったのも同時期で、エリス・レジーナの『In London』とか、やはりきっかけは『太田コーナー』でしたね。」
H「そして渋谷系。岩間さん、東京の文科系男子のまさに王道を歩いてますね。ではそろそろモイさんへのお話を教えていただけますでしょうか。」
I「北欧との出会いはやはり90年代半ば、家具や建築デザイン、そしてスウェディッシュポップスを通してでした。初めてカーディガンズやクラウドベリージャムを聴いたとき、『まだこんな(80年代のNWのような)音楽をやっている連中がいるのか!』と仰天したのを憶えています。父が何十年もデンマーク人と文通していて、幼い頃からよく話を聞かされたりしていたのでなんとなく北欧に対する親しみはありましたね。とりあえず、こんな音楽や家具をつくる人たちが暮らす国をこの目で見てみたい、そう思ってフィンランドへ行ったのが1999年のことです。フィンランドを選んだのは、建築家のアルヴァー・アールトやデザイナーのカイ・フランクの作品にもっとも惹かれていたからです。実際ににフィンランドに行ってみて、日本の古き良き喫茶店文化を、北欧、とりわけフィンランドのデザインというをフィルターを通して表現したら他にない空間ができるかもしれないと感じました。一度、そう思ってしまったが最後、もういてもたってもいられない。2001年に『Bunkamura』を退職し、2002年、荻窪に6坪弱のちいさなカフェ『moi』をオープンしました。ぼくが『Bunkamura』をやめて『moi』を始めたことは、周囲の目には奇異なことのように映ったみたいでいろいろなことを言われました。でも、ぼく自身の中では、それはどちらも『箱』をつくり、育てる仕事という点で同じだと思っていたし、実際、劇場の運営や企画に携わっていたころに学んだことはいまも役立っています。2002年というタイミングはちょうど雑誌などがこぞって『北欧』を取り上げ始めたころでしたが、まだ世間一般の認知度は低く、お客様から『なぜ北欧なの?』と怪訝な表情で尋ねられたり、『フィンランド』ではなく『フィリピン』と間違えられたり、店名を見てフランス人が入ってきたりしました(笑)。」
H「(笑)。あ、やっぱりそういうフランス人いるんですね。ちなみにどうして荻窪と吉祥寺だったんでしょうか?」
I「中央線の沿線は、当時からじつは北欧文化となじみのあるエリアでした。中野に『スオミ教会』が、高円寺にフィンランド人専用の下宿『ネコタロ』が、阿佐ヶ谷には当時『ミナ・ペルホネン』の皆川明さんのアトリエが、西荻窪にはかつてスウェーデン料理の『リラ・ダーラナ』が、そして吉祥寺にはやはりスウェーデン料理の老舗『ガムラスタン』がありました。昔からこだわりのある人が多く暮らし、北欧文化にも理解が深そうな場所ということで荻窪で5年半、その後、縁があって吉祥寺に移転します。そこそこ都会でありながら生活の匂いがあり、水と緑(井の頭公園)がある吉祥寺を、あるお客様は『海のないヘルシンキ』などと呼んでいますが(笑)、じっさい、そうしようと思えば、東京にいながらにしてフィンランドのようなペースで過ごせるのが吉祥寺という土地だと思っています。」
H「なるほどなるほど。今でこそモイさんは吉祥寺というイメージですが、そういうことなんですね。さて、これはみんなに質問していることなのですが、これから音楽はどうなっていくと思いますか?」
I「『なるようにしかならない』のではないでしょうか? 音楽をやりたいひとがいて、聴きたいひとがいる。そして、よい音楽と出会えばそれを誰かに教えたくなる。いまもむかしも、音楽を支えてきた最小単位はそこにあるのであって、それはこれからもずっと変わらないでしょう。ビジネスとしてそれでゴハンが食べられるかどうかというのはたんなる『業界』の問題でしかないので、『業界』のひとが一生懸命に考えればいいことだと思ってます。」
H「うーん、これ色んな方が色んなお答えをしてくれるのですが、『たんなる業界の問題でしかない』というのが本当に岩間さんらしいお答えですね。では最後に岩間さんのこれからのことを教えていただけますか。」
I「結局、ぼくの最大の関心事は空間、『箱』にあるみたいです。なにを、どのように満たせばその『箱』がもっと面白く、感動的な空間になるのか? たとえば、みんなが、そして自分がカフェに飽きてしまったのなら、べつにカフェという型にこだわる必要はないと考えています。なので、当初から『cafe moi』ではなく、このお店の正式名称は『moi』としています。『これ!』というものと出会ったら、不意になにかちがうことを始めるかもしれません(笑)。まあ、いまのところ『北欧』を超える関心事はないのですけどね。」
H「わわわ。最後にすごいお言葉が出ましたが、僕らはホント『箱』ですよね。身が引き締まるお話でした。さて、そろそろ選曲に移りたいのですが、まずテーマを教えていただけますでしょうか。」
I「はい。『真ん中よりも、ちょっと外れたところにいたいひとのための10曲』です。どうやらぼくは、輪の中心にはなれない人間のようです。中心になりたくないのかというと全くそういうことはなくて、むしろ色気はたっぷりあるのですが、いざなにかの加減で中心になってしまったりすると、今度はどうにもいたたまれなくなってさっさと逃げ出したい気分になってしまう。それならいっそのこと完全に外れて、アウトローになってしまえばよいのでしょうが、残念ながらそういう柄でもない。結局ぼくにとっていちばん居心地がいいのは、『中心よりもほんのちょっと外れたところ』らしいのです。とはいえ、うかつに中心に近づきすぎると、遠心力で一気に遠くまで弾き飛ばされてしまいます。飛ばされないように必死で踏ん張りながら、でもときどき飛ばされてはまた戻ってくる。そんなふうに、行きつ戻りつしながらなんとか自分の居場所を探し続けている、それがぼくの人生という気がします。ただ、先日たまたま読んだ東京出身のコラムニストが書いた本によると、それこそ筋金入りの『東京っ子』気質らしいのですが......。」
H「なるほど。僕もいつも『どうして岩間さん、中心に走らないんだろう』って思ってたのですが、そういう感覚なんですね。ますます選ぶ曲が気になりますが。」
I「はい。ここでは、そんなぼくが人生の曲がり角で出会い、強く心惹かれてきた音楽を10曲選んでみました。『〝東京っ子〟に捧げる10曲』といってもいいかもしれません。案の定というべきか、なんだか安定のよくない、晴れているのか曇っているのかよくわからないような10曲が並びました。最高(笑)。」
1.ドラマ『水もれ甲介』オープニングテーマ
I「子供のころ、テレビやラジオをつけると耳に飛び込んできたバカラック調のメロディー。そんな数多い『バカラック調』のなかでも、大野雄二の手になるこの曲は『決定版』ではないでしょうか。石立鉄男主演のドラマ同様、この主題歌も大好きでした。まさに回転木馬のような、永遠に〝閉じない〟メロディー。」
H「うわ。おもいっきりバカラック・マナーですね。大野雄二のこんなの知りませんでした。最初からすごいのを聞いてしまいましたが...」
2.Billy Joel / My Life
I「中1のとき、おじさんの家でひとりラジオの深夜放送を聴いていたらこの曲が流れてきたのですが、そのとき、生まれてはじめて音楽を聴いて〝気持ちよすぎて気持ちわるくなる〟という体験をしました。具体的には、エレピのフレーズ。波打ち際で遊んでいると、波が引くとき一緒に身体まで持ってゆかれるように錯覚することがありますけど、まさにそんな、どこに連れ去られるかわからないような不安感に『都会の孤独』のようなものを感じました。」
H「永遠の良い曲ですよねえ。次はどうでしょうか?」
3.マーラー交響曲第4番ト長調より第1楽章
I「これもたしか、中1のときに出会った音楽です。当時、マーラーの音楽はいまほどポピュラーではなく、それを聴くことにはどこか『背徳の香り』がつきまとっていました。ドキドキしながら針を落とすと、そこには見たこともない甘美でサイケデリックな景色が広がっていて言い様のない衝撃を受けたのを憶えています。作曲家としてはまともな評価をされないまま、でも『やがて私の時代がくる』という予言を残してこの世を去ったマーラー。100年後その予言は的中するわけですが、彼もまた、生涯を通して中心からちょっと外れたところでもがいていたという気がします。」
H「岩間さん、何かクラシックはくると予想していたのですが、マーラー! 中心からちょっと外れたところでもがいていた... 岩間さん... 次は?」
4. Kieth West / On A Saturday
I「どこかにまだ平日を引きずっている、そんな土曜日の中途半端な開放感が好きです。この曲の印象は薄曇りなんですが、途中一瞬だけ日が射します。高校時代の大半はほとんど同時代の洋楽は聴かず、ひたすらこういった60年代の音楽ばかりラジオで聴いてました。」
H「あ、僕、実は岩間さんってこの辺りの感じがメインの人だってずっと思ってたので、ちょっとホッとしています。次は?」
5.Naked Eyes / Always Something There To Remind Me
I「17歳のとき、ザ・スミスなどとともにぼくの耳を同時代のイギリスへと駆り立ててくれた曲のひとつです。ヒューマンリーグ、ヤズー、チャイナクライシス、デペッシュモードなどと並ぶいわゆる『エレポップ』のバンドのひとつですが、バート・バカラックの曲をこんなアレンジでカバーしてしまう才能に舌を巻きました。NWと60年代ロックの『親和性』を象徴する佳曲だと思います。」
H「今聞いたらどうだろうと思ったら、なんかいけますね。若い人の感想を聞いてみたい演奏です。次は?」
6.Alaide Costa / Catavento
I「90年代後半、『Blue Brazil』というコンピCDで知った曲です。以前このブログにも登場した友人の田仲君に連れられて、はじめてバールボッサにお邪魔したのもちょうどこの頃です。当時、この曲を収録したアルバムが見つからず、やむなく入手可能なAlaide CostaのCDを何枚か買ったのですが、情感たっぷりのサンバカンサォンばかりでがっかりしたのを憶えています。それはそれで悪くはないのですが......。きっとこの作品が、彼女のディスコグラフィーのなかでは『異色』なのでしょう。そういう『徒花』的なものにまず惹かれるというのも、いかにもボクらしいなと自分で思います。」
H「岩間さん、これお好きなんですね。知りませんでした... 確かに徒花ですよね。うーん。なんだか次が気になってきましたが。」
7.長谷川きよし / 卒業
I「女性が永遠に『女子』だというのなら、男性は永遠に『中2』なのです。移動遊園地をつくる夢を追いかけながら、実際にはおんぼろのルノー5に乗って若い娘のお尻を追っかけ回しているイヴ・モンタン主演の映画『ギャルソン』や、『花屋をさがしているうちに春はどこかに行っちゃった』と呟くこの曲の主人公に自分の姿を重ね合わせることができるのはまちがいなく男の特権。ちなみに、はじめてこの曲を聴いたのはムーンライダースによる秀逸なカヴァーでした。」
H「僕が待っていた岩間さんの世界が出て来ました! 次はどうでしょうか?」
8.一丁入り
I「すべての落語家には、その登場にあわせて演奏される『出囃子』と呼ばれる音楽があります。これは、そのなかでぼくがもっともカッコいいと思っている出囃子で、古今亭志ん生の『一丁入り』という出囃子です。台風もいちばん激しいのは『目』よりもそのちょっと外側だったりしますが、志ん生の『芸』にも、聴くものを巻き込んでゆく激烈な台風のような勢いがあります。」
H「岩間さん、今は落語なんですよね。たまにツイッターですごく情熱が伝わってきます(笑)。落語イベントが来る日も近いのでしょうか... そろそろ最後が近づいてきましたが。」
9.Dirty Projectors / About to Die
I「スタッフに教えてもらいました。2012年にリリースされたブルックリン出身のバンドの曲です。Vimpire WeekendとかDarwin Deezとか、ここ数年いいなと感じたアーティストにはブルックリン出身が多いです。マンハッタンというNYの中心ではなく、そこからわずかにずれたブルックリンのバンドに心惹かれるというのも偶然なのか必然なのか、いずれにしても僕らしいなと思います。」
H「岩間さんの80年代のインディーズ話を聞いた後ではすごく納得のPVですね。では最後になりますが?」
10.武満徹編 / The Last Waltz
I「晩年の武満には、「『うた』のひと」というイメージがあります。それをもっとも強く感じさせるのは『編曲家・武満徹』ですね。彼が編曲した作品を聴いていると、まるで彼の『うた』への愛がこぼれ落ちてくるようです。武満は世界的な作曲家であり、その意味で音楽の『よい作り手』であったわけですけど、同時に最高に『よい聴き手』でもあったのではないでしょうか。」
H「うわ、こんなのがあるんですね。最後に美しくまとまりました。」
岩間さん、今回はお忙しいところどうもありがとうございました。
ご存知かとは思いますが、岩間さんのツイッター、独特の東京っ子の笑いで楽しいですよ。さらに最近はフェイスブックも始めたそうです。フォローしてみてはいかがでしょうか。
●moi facebook→ https://www.facebook.com/moicafe
●moi twitter→ https://twitter.com/moikahvila
季節はあっという間に冬らしくなって来ましたね。それではまたこちらのお店でお待ちしております。
bar bossa 林伸次
【バーのマスターはなぜネクタイをしているのか? 僕が渋谷でワインバーを続けられた理由】
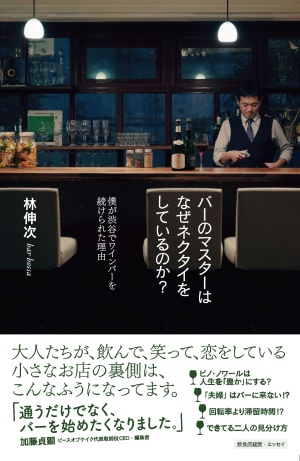
Amazon商品ページはこちら
| bar bossa information |
林 伸次
1969年徳島生まれ。
レコファン(中古レコード店)、バッカーナ&サバス東京(ブラジリアン・レストラン)、
フェアグランド(ショット・バー)を経た後、1997年渋谷にBAR BOSSAをオープンする。
2001年ネット上でBOSSA RECRDSをオープン。
著書に『ボサノヴァ(アノニマスタジオ)』。
選曲CD、CDライナー執筆多数。
連載『カフェ&レストラン(旭屋出版)』。
bar bossa

●東京都渋谷区宇田川町 41-23 第2大久保ビル1F
●TEL/03-5458-4185
●営業時間/月~土
12:00~15:00 lunch time
18:00~24:00 bar time
●定休日/日、祝
●お店の情報はこちら
|
j








 RSS
RSS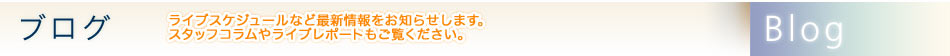

























![j-0907_img_1[1].jpg](http://www.jjazz.net/jjazznet_blog/img/blog/j-0907_img_1%5B1%5D.jpg)