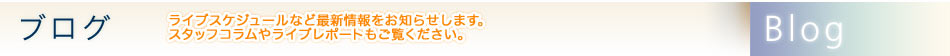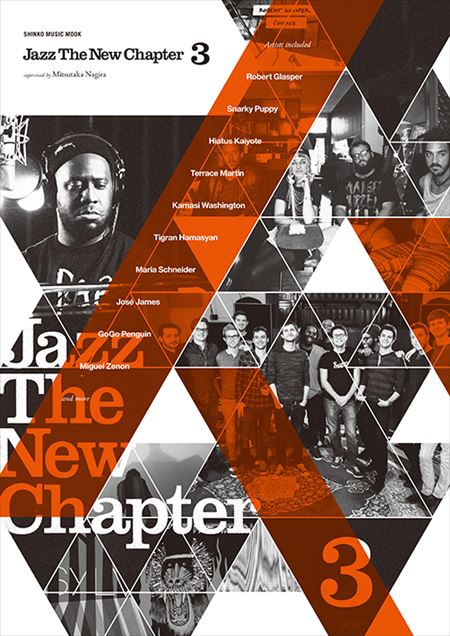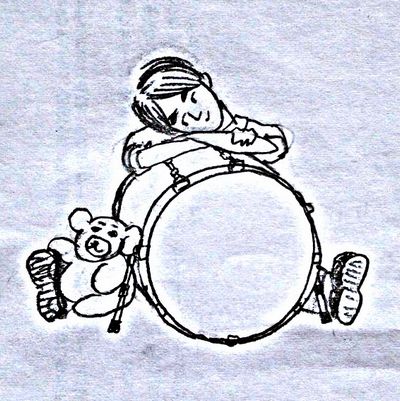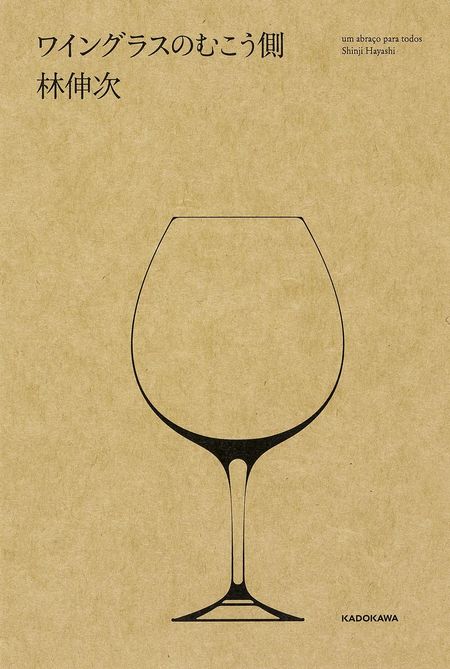CRCK/LCKSインタビュー
ポップスシーンに突如現れた異能の集団"CRCK/LCKS"(クラックラックス)。結成から1年も経たずにその噂は拡散し、今年4月にはついにアルバムをリリースした。それぞれのルーツミュージックが濃厚に詰め込まれたハイブリッドなサウンドは、明らかにポップの様式美からはハミ出ているが、彼らはそれをとてもナチュラルに鳴らす。そんな彼らの音楽性は、彼らがみな何処か一側面ではジャズ・ミュージシャンであることと切り離せない。
今回は小西遼(Sax, Vocoder, etc,)、小田朋美(Vo, Key)、角田隆太(B)、井上銘(Gt)、石若駿(Ds)というメンバー全員と本作のプロデューサーである阿部氏を迎えて、それぞれのルーツやレコーディングについて、そして彼らが肌で感じるシーンの現状について話を聞いた。
インタビュアー:花木洸 HANAKI hikaru(音楽ライター)
ライブをするまでは誰も長続きすると思ってなくて。
――まずはメンバーそれぞれの経歴について聞きたいな。まず角田くんからお願いします。
[角田] ――最初は普通にロックバンドをやっていたんですか?
[角田] ――なるほど。じゃあ、銘くん。
[井上]
[小西]
[井上] ――「ジャズだ!」って決めたきっかけは何だったんですか?
[井上] ――なるほどね。じゃあ石若くん。
[石若]
[小西]
[石若]
[一同]
[小西]
[石若] ――じゃあ次はリーダーの小西さん。
[小西]
[小田]
[小西] ――菅野よう子だ。
[小西]
[角田]
[井上]
[小西]
[石若]
[小西] ――じゃあ今やってるのはこのバンドとラージアンサンブル?
[小西] ――なるほどね。じゃあ最後に小田さん。
[小田]
[井上]
[小田] ――へぇー。
[小田] ――うわぁ、暗躍してますね(笑)
[阿部]
[小西]
[阿部]
[小田] ――バンド結成の話を教えてください。
[小西]
[阿部] ――じゃあ結成しようってなって、とりあえずスタジオに入って、みたいな?
[小田]
[小西]
[角田]
[井上]
[一同]
[小西] 一番最初にみんなで音を出して感じたのはブラック・ミュージック的な要素だった ――この5人で集まった時に、音楽的な共通項って何だったんですか?
[小西]
[石若]
[小西]
[石若] ――今回のアルバムは曲をみんなで持ち寄ったってことなんだけど、スタジオでの曲作りはどういう風にして進んでいったんですか?
[小西] ――なるほどね。僕は音源を聴いてセッションぽくやってるのかな?って思ったんです。とくにドラムとかベースの、良い意味でラフな感じ。
[石若]
[一同]
[小西]
[石若]
[角田]
[小西]
[石若] ――レコーディングされたものはソロがコンパクトになったり色々ライブとは変わっていたよね。
[小西] ――レコーディングはどれくらい時間かけたんですか?
[小西] ――6曲で録音2日?!かなり素早くやらないとですね。
[小西]
[小田] ――へぇー。
[小西]
[井上]
[小西]
[小田] ――今回はミックスもこだわっていたみたいだけど、ミックスする時にどんな音像を目指してたとかあります?
[小西]
[角田] ――「いらない」でパーカッションが重なったりしてるのも....。
[小西]
[小田]
[小西] ――「クラックラックスのテーマ」では電子レンジまで入ってましたもんね。
[石若]
[小西]
[角田] 【CRCK/LCKS 1st EP予告編】 VIDEO [小西]
[井上]
[小西]
[井上]
[小西] ――僕はレコーディング前とレコーディング後両方ライブを観てるんだけど、やっぱり後のほうが面白かったんだよね。
[一同] ――え、本人たちはあんまり実感無いですか?(笑)
[井上] ソロが長くなってもそれは曲に必要な要素なだけであって、僕達がジャズ・ミュージシャンだからってわけではない。 ――クラックラックスとしての「ポップの条件」って何かあります?このバンドは普段ジャズを演奏しているメンバーが所謂バンドのサウンドを作ってるわけじゃないですか。その中で何か意識の違いだとか。
[井上]
[小西]
[井上]
[小西]
[角田]
[井上] ――じゃあ意識的にはジャズをやる時と一緒って感じですか?
[石若]
[井上]
[石若]
[小西]
[小田] ――その作詞に関してもうちょっとききたいんだけど、「スカル」だけ園子温さんの詩なんですよね。違う人が書いた詞を持ってくる感じは、僕としてはクラシックっぽい発想だなって思ったんです。違うモチーフを持って来てその上で創作をするっていう。
[角田]
[小田] ――ライブではマザーグースの詩(Little Bo Peep)の寺山修司訳に音楽をつけたりもしていましたよね。
[小西] 【そして彼女達は前を向く - 象眠舎 (旧:小西遼ラージアンサンブル)】 VIDEO シーンが変わったというか、角田がシーンを作った ――角田さんは、ものんくるでも詞を書いているんですよね。
[角田]
[小西]
[井上]
[小西]
[角田]
[井上]
[角田] ――ジャズのシーンにいてもやっぱり変化があったんですか?
[小西]
[角田]
[井上]
[小西]
[角田]
[石若]
[小西]
[小田]
[小西]
[石若]
[小西] ――クラックラックスも「ハイブリッドな歌もの」としても聞けそうですよね。
[小西]
[井上]
[小西]
[角田] 【「Goodbye Girl」PV CRCK/LCKS】 VIDEO
CRCK/LCKS 1st EP「CRCK/LCKS」Release Live
【東京】http://www.moonromantic.com/?p=30067 http://www.tokuzo.com/schedule/2016/06/620crcklcksthe-pyramid.php http://www.arm-live.com/2nd/index.html#ticket
New Album
Title : 『CRCK/LCKS』
【MEMBER】
【SONG LIST】
【CRCK/LCKS】
2015年4月に結成。
5人の若き才能が結集して作られるハイクオリティなポップミュージックは耳の早い音楽ファンの間では既に話題となっている。2016年4月、パーカッショニストのASA-CHANGをゲストに招き、待望の1stミニアルバム『CRCK/LCKS』をリリース。
CRCK/LCKS BLOG
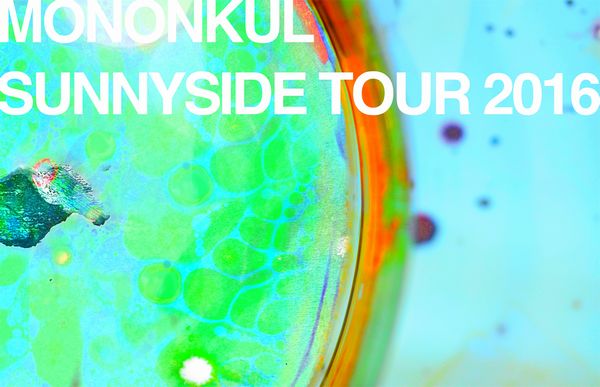



 RSS
RSS