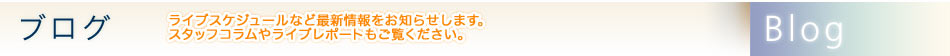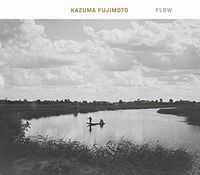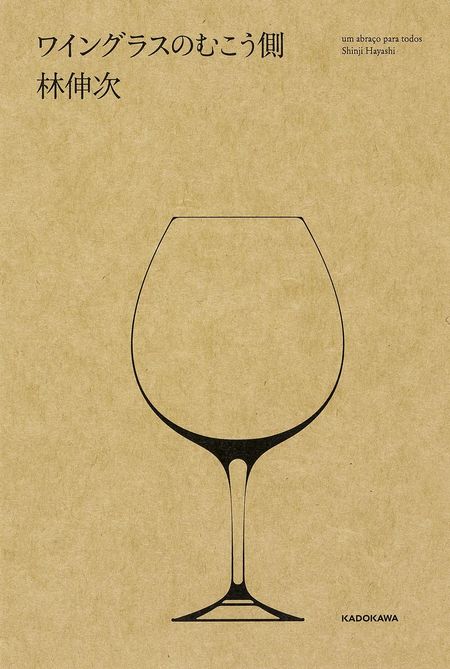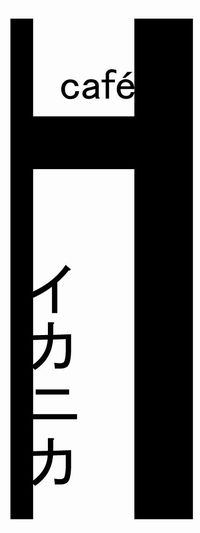vol.56 - お客様:渡部徹さん
今回はpwmの名前で選曲家として有名な渡部徹さんをゲストに迎えました。林; こんばんは。早速ですが、お飲物はどうされますか?渡部; 林; じゃあ、ブルゴーニュのピノ・ノワールにしますね。ところでお生まれは?渡部; 林; あ、そうでしたか。小さい頃の音楽環境を教えてもらえますか?渡部; 林; 良いご両親ですね。渡部; 林; なるほど。渡部; 林; やっぱり同世代ですね。僕も帽子、投げましたよ。渡部; 林; なんか僕と全く同じです。自分の話みたいです(笑)。渡部; 林; おおお、宅録職人でしたか。なんかわかるような気がします。渡部; 林; 1990年がその2枚だったんですね。サバービアも本当に当時は衝撃的でしたよね。渡部; 林; わかります、わかります。今回はずっとうなずいていそうです(笑)。渡部; 林; そこで地元で活動するのが渡部さんらしいですね。渡部; 林; この須永さんとのお仕事が渡部さんをすごく有名にしたんですよね。さて、これみんなに聞いているのですが、これからの音楽はどうなると思いますか?渡部;
まず作り手側ですが、これからは良い音楽を作って発表する若者が増えるだろうと楽観しています。例えば、ぼくが凄い時間とお金をかけてやっと聴くことができたコアな音楽が、YouTubeとかで簡単に聴けるようになりましたよね。特に若くて多感な子にはメリットが大きいと思います。それから、音楽を作ったり発表するのハードルが圧倒的に下がったこと。パソコン一台あればそこそこの音楽ができて、SoundCloudやYouTubeでアップできますからね。もう、いまの若い人たちが羨ましいです(笑)。
次に売り手側ですが、いま音楽マーケティングは、大変革の真っ只中だと思っています。1967年のビートルズ『サージェント・ペパーズ』以降、アルバム単位でアートフォームを作り上げるのが至上とする風潮があったじゃないですか。それがiTunesやYouTubeの登場以降、曲単位でのリリースが主体になってきた。つまり今はある意味60年代以前のシングル盤の時代に戻っているというか、一曲でもいい曲ができれば全く無名の音楽家が脚光を浴びるようになったと。音楽ビジネスもCD販売ではない何かに変わっていくのでしょう。想像もできないフォーマットが今後生まれてくると思うと、ちょっとワクワクしますね。林; 音楽の現状や未来を楽観的に感じているのがすごく渡部さんらしくて良いですね。さて、渡部さんのこれからの活動の予定みたいなのを教えてもらえますか?渡部;
オルガンバーWebのレビューでずっと一緒に活動していたデシネの丸山雅生さんとは「今度○○をしたいねえ」と話しているのでご注目ください。あと、地元では細々とクラブイヴェント的なことを企画したり、プエルトムジカ(Puerto de la Musica)というユニットでイヴェント企画やフリーペーパー発行したりしています。この活動はこれからも続けていきたいです。林; 東京じゃない場所で音楽を愛する人の理想的なスタイルですね。ではみんなが待っている選曲ですが、まずはテーマを決めていただきたいのですが。渡部; 林; おお、渡部さんセレクトの東アジア音楽、期待いたします!01. Joohye / Biggest Fan VIDEO
渡部;
林; おおお、ネオアコ直球ですね。Joohye、確かにかわいいです...(笑)02. 旺福 / 夏夕夏景 VIDEO
渡部;
林; まさにフリッパーズ・ギターのことがすぐに思い浮かびますね。でもどこか台湾で独特ですね。03. La Ong Fong / It's all you VIDEO
渡部;
林; タイはやっぱりタイ語の言葉の響きがメロディーに影響を与えて独特の雰囲気になりますね。良いですねえ。04. Tulus / Kisah Sebentar VIDEO
渡部;
林; 本当だ。すごい展開ですね。日本人にはちょっと思いつかないようなアイディアですね。05. Joanna Wang / Vincent VIDEO
渡部;
林; うわあ、すごい本格的な良い声ですね。でも確かにアン・サリーや畠山美由紀のような「どこかアジア」が感じられますね。06. Operation Bangkok VIDEO
渡部;
林; 渡部さん、ほんと、聴いている音楽の幅が広いのに、どれもがどこか「pwm色」が感じられてすごい稀有な才能ですね。東京でいたらと思うのですが、東京でいないからこういうセンスなのでしょうか。07: What Women Want / Curious VIDEO
渡部;
林; これすごく良いですね。韓国って男性ヴォーカルの本格具合が「日本にはない感じ」なんですよね。日本ロケっていうのがなんか不思議で嬉しいし。08: Maliq & D'Essentials / Penasaran VIDEO
渡部;
林; インドネシアって「メロウ」ですね。MVがすごくハッピーで羨ましい風景です。09: Nangman Band / Spring VIDEO
渡部;
林; 韓国は本当に「切ない」がキーワードですね。必ず「青臭さ」みたいなものを音楽にいれてきますね。10: Jung Jae Hyung / Pour Les Gens Qui S'Aiment VIDEO
渡部;
林; この人はやっぱり「日本からは出てこないタイプの音楽だなあ」っていつも感じますね。でもやっぱりアジアを少し感じます。pwm twitter
【林 伸次 近著】
■タイトル:『ワイングラスのむこう側』
bar bossa information
林 伸次 bar bossa お店の情報はこちら

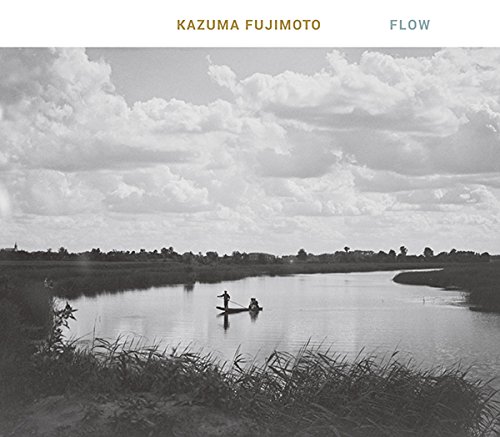
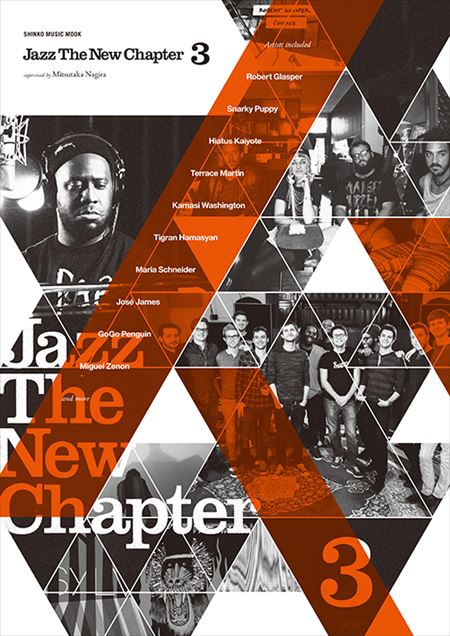
![]()
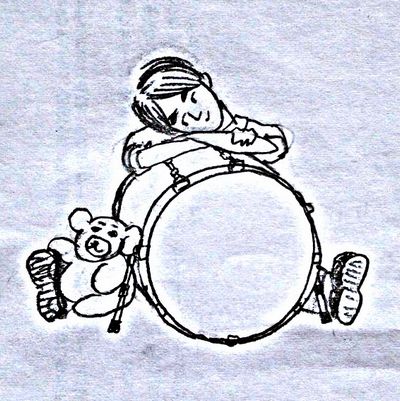


 RSS
RSS